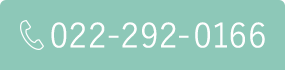- 月経(生理)がつらいと感じたら、それは異常かもしれません
- 月経異常(月経の周期や出血量のトラブル)
- 月経困難症(月経に伴う強い痛み)
- PMS・PMDD(月経前のこころと身体の不調)
- 月経に関連したトラブルの治療法について
月経(生理)がつらいと感じたら、それは異常かもしれません
 月経は多くの女性が毎月経験する自然な身体のサイクルです。しかし、その月経に伴う症状や変化が「日常生活に支障をきたす」「精神的にもつらい」と感じる場合、それは何らかのトラブルが隠れているサインかもしれません。
月経は多くの女性が毎月経験する自然な身体のサイクルです。しかし、その月経に伴う症状や変化が「日常生活に支障をきたす」「精神的にもつらい」と感じる場合、それは何らかのトラブルが隠れているサインかもしれません。
このページでは、月経にまつわる代表的な3つのトラブル(①月経異常、②月経困難症、③PMS/PMDD)について、それぞれの特徴や原因、受診の目安、治療法まで解説します。
婦人科受診の目安
- 月経(生理)が3か月以上来ない、または頻繁に来る
- 出血量が極端で、日常生活に支障がある
- 月経(生理)痛が強く、薬が効かない
- 月経前に毎月イライラ・気分が落ち込みすぎる
- 不正出血がある/妊娠の可能性がある
月経トラブルは体質だけのせいではなく、治療で改善できるものも多くあります。気になる症状がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
月経異常(月経の周期や出血量のトラブル)
月経は、女性の健康状態やホルモンバランスを反映する大切なサインです。 しかし、周期が不安定だったり、出血量が多すぎたり少なすぎたりする場合、何らかの体の不調や病気が隠れている可能性があります。
当院では、過多月経の診断で挿入する子宮内黄体ホルモン放出システム(
こんな症状はありませんか?

- 月経(生理)が来ない、何か月も止まったままになっている(無月経)
- 月に2回以上月経(生理)がくる(頻発月経)
- 月経(生理)がなかなか来ない、40日以上あいてしまう(稀発月経)
- 出血量が非常に多く、夜用ナプキンでも対応できない(過多月経)
- 出血量が極端に少なく、ナプキンがほとんど汚れない(過少月経)
- 毎月の月経(生理)周期がバラバラで安定しない
- 月経(生理)以外の時期に出血がある(不正出血)
こうした症状は、一時的な体調変化によるものの場合もありますが、繰り返す・長引くようであれば、放置せずに婦人科での診察を受けることをおすすめします。
月経異常の主な原因
- 思春期や更年期に起こるホルモンバランスの乱れ
- ストレスや過度なダイエット、急激な体重減少や増加
- 子宮筋腫・子宮内膜症・卵巣のう腫などの器質的疾患
- 甲状腺機能の異常や高プロラクチン血症などの内分泌異常
- 排卵障害(多嚢胞性卵巣症候群:PCOS など)
月経異常に関するよくある質問(Q&A)
月経が月に2回あるのは異常ですか?
通常の月経周期は25〜38日程度ですが、これより短い周期で繰り返す場合は「頻発月経」と呼ばれます。黄体機能不全や無排卵周期、甲状腺の異常などが原因となることもありますので、毎月のように頻繁に起こる場合は婦人科での検査をおすすめします。
月経(生理)が2か月に1回しか来ないのですが、大丈夫でしょうか?
月経周期が39日以上空く場合は「希発月経」とされ、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)や高プロラクチン血症、ストレスや体重変化によるホルモンバランスの乱れが原因となることがあります。周期が不規則な場合は排卵障害が関係している可能性もあり、将来の妊娠を考える方は特に早めの受診が望まれます。
月経(生理)が3か月以上来ていません。これは無月経ですか?
はい、妊娠や閉経ではないのに3か月以上月経が来ない場合、「続発性無月経」と診断されます。視床下部や下垂体の機能低下、早発卵巣不全(POI)、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)など、さまざまな原因が考えられます。放置すると将来的な不妊や骨密度低下のリスクもあるため、早めの婦人科相談をおすすめします。
出血量が多くて困っています。過多月経の原因は何ですか?
経血量が140mLを超える場合、過多月経とされます。原因としては、子宮筋腫(特に粘膜下筋腫)、子宮腺筋症、子宮内膜増殖症などが考えられます。出血が多くて貧血や生活への支障がある場合は、検査と治療が必要です。
月経(生理)の出血がとても少なく、1日で終わってしまいます。異常でしょうか?
出血量が20mL以下であったり、1〜2日で終わってしまう場合は「過少月経」と呼ばれます。黄体機能不全、子宮内膜の菲薄化、低エストロゲン状態、子宮内腔癒着症などが原因として考えられます。継続するようであれば婦人科での精査をおすすめします。
月経(生理)が8日以上続いています。これは過長月経ですか?
はい、月経が8日以上続く場合は「過長月経」に分類されます。卵胞発育不全や子宮筋腫・腺筋症、血液の凝固異常(例:von Willebrand病)などが背景にあることがあります。特に出血量も多い場合は、貧血や日常生活への影響もあるため、婦人科受診が必要です。
月経周期が毎月違っていて不安です。何が原因でしょうか?
月経周期が安定しない場合、ホルモンバランスの乱れや排卵障害が関係していることが多く、ストレス、過労、過度なダイエット、睡眠不足などが影響します。慢性的な周期の乱れは婦人科疾患の兆候である可能性もあるため、基礎体温を記録しながら医師に相談するとよいでしょう
無月経を放置すると、体にどんな影響がありますか?
無月経を長期間放置すると、排卵がないことによる不妊のリスク、エストロゲン不足による骨密度の低下や将来的な骨粗しょう症、生活習慣病リスクの上昇などが懸念されます。月経(生理)が止まってしまったときは、早めに原因を突き止め、適切な治療を受けることが大切です。
月経異常は妊娠に影響しますか?
はい。無月経や稀発月経、無排卵周期症は、排卵が不規則または起こっていない可能性があり、妊娠のしにくさ(不妊)に直接つながります。将来的に妊娠を希望される方は、早めにホルモン検査や排卵の有無を確認することをおすすめします。
月経異常は治療で改善しますか?
多くの場合、原因に応じた適切な治療によって月経異常は改善が可能です。ホルモン療法(低用量ピル、黄体ホルモン剤)、ライフスタイルの改善、栄養管理、漢方薬などが用いられます。器質的疾患がある場合は手術が必要になることもありますが、まずは原因の診断が大切です。
月経異常は、放置すると不妊症や貧血、日常生活への支障につながることがあります。 「なんとなく不調」「月経(生理)が来ない月がある」といった場合でも、早めの受診と検査で原因を特定し、適切な治療を行うことが重要です。 どんな小さな症状でも、お気軽にご相談ください。
月経困難症(月経に伴う強い痛み)
月経困難症とは、月経(生理)のたびに強い下腹部痛や腰痛などの不快な症状が現れ、日常生活に支障をきたす状態を指します。 思春期の若年女性から出産後の世代まで、幅広い年代でみられる代表的な婦人科症状のひとつです。
当院では、月経困難症の診断で挿入する子宮内黄体ホルモン放出システム(
月経困難症の主な症状

- 月経(生理)開始とともに起こる下腹部痛や腰痛
- 吐き気や下痢、頭痛、倦怠感
- 集中力の低下や情緒不安定
- 鎮痛薬を飲んでも痛みが和らがらない
- 学校や仕事を休まざるを得ないほどの強い痛み
このような症状が毎月のように続く場合は、単なる“体質”ではなく、医療的な治療が必要な状態かもしれません。
月経困難症の2つのタイプ
月経困難症には、原因に応じて「機能性」と「器質性」の2種類に分類されます。
機能性月経困難症
- 子宮や卵巣に明らかな病気がないタイプ
- 排卵に伴い、子宮内膜からプロスタグランジンという痛みの原因物質が過剰に分泌されることが主な原因
- 子宮の強い収縮や血流障害によって痛みが生じます
- 思春期〜20代前半の若年女性に多く見られます
器質性月経困難症
子宮や卵巣に明確な病気がある場合に生じるタイプ
主な原因疾患には以下が含まれます:
- 子宮内膜症
- 子宮腺筋症
- 子宮筋腫(特に漿膜下・筋層内筋腫)
20代後半以降に多くみられ、加齢とともに症状が強くなる傾向があります
月経困難症に関するよくあるご質問(FAQ)
月経(生理)のたびに強い腹痛があります。これって病気ですか?
毎月のように強い月経(生理)痛がある場合、「月経困難症」と考えられます。ホルモンによる一時的な痛み(機能性)と、子宮内膜症や子宮筋腫などの病気(器質性)によるものがあり、原因に応じた治療が必要です。
月経困難症にはどんな種類がありますか?
月経困難症には主に2つのタイプがあります。
1つは機能性月経困難症で、明らかな病気がなく、排卵後に分泌されるプロスタグランジンの影響で痛みが強くなるものです。もう1つは器質性月経困難症で、子宮内膜症や子宮筋腫などの病気が原因で起こるものです。
月経(生理)痛がひどいのは体質のせいですか?
必ずしも体質だけが原因とは限りません。とくに鎮痛薬が効かない、痛みが年々ひどくなるなどの症状がある場合は、子宮内膜症などの病気が隠れている可能性があります。医師の診察を受けることをおすすめします。
月経(生理)痛のために毎月学校や仕事を休んでいます。治療できますか?
はい、月経困難症は適切な治療で症状の軽減が期待できます。鎮痛薬、低用量ピル、漢方薬など、症状に応じた治療法がありますので、我慢せず婦人科にご相談ください。
低用量ピルは月経(生理)痛に効果がありますか?
低用量ピルは排卵を抑え、プロスタグランジンの分泌を抑制することで、月経(生理)痛を軽減します。また、月経の出血量を減らし、周期を安定させる効果もあります。ただし、使用には医師の処方が必要です。
鎮痛剤が効かないのですが、どうしたらよいですか?
鎮痛薬が効かない場合は、器質性の病気が原因の可能性があります。子宮内膜症や子宮腺筋症などがあると、通常の鎮痛薬では対応しきれないことがあります。早めに婦人科で原因を調べることが大切です。
子宮内膜症があると、どんな症状が出るのですか?
子宮内膜症では、強い月経痛、性交痛、排便時の痛み、不妊などの症状が見られます。月経のたびに痛みが増していくようであれば、内膜症の可能性があり、画像検査などによる診断が必要です。
月経困難症は年齢とともに治りますか?
思春期の機能性月経困難症は、年齢とともに軽くなる場合もありますが、器質性の場合は加齢とともに悪化することもあります。出産によって改善するケースもありますが、全ての人に当てはまるわけではありません。
妊娠したら月経困難症は治りますか?
妊娠・出産後に月経(生理)痛が軽くなる方もいますが、内膜症や筋腫などの病変がある場合は症状が再発することもあります。妊娠によって一時的に月経が止まることで楽になることはありますが、根本的な治療にはなりません。
手術が必要になることはありますか?
器質的な原因(たとえば子宮筋腫や内膜症)が重度の場合や、薬物療法で効果がない場合は、手術が選択肢になることもあります。内視鏡による低侵襲手術が可能な場合もありますので、まずは医師とご相談ください。
月経困難症は、症状の現れ方や感じ方、治療の効果などに個人差が大きいのが特徴です。 そのため、治療を始める前には、超音波検査(子宮・卵巣の形態評価)や血液検査(貧血の有無・女性ホルモン・甲状腺・炎症反応など)を行い、原因を正確に把握することが重要です。月経痛は「仕方がないもの」と思われがちですが、現代の医療では効果的な治療が多数あります。
症状だけで自己判断せず、専門医による評価を受けたうえで、体質やライフステージに合った最適な治療法を一緒に考えていくことが大切です。
毎月つらい症状に悩まされている方は、ぜひ一度、婦人科で相談してみましょう。早期の対処によって、生活の質(QOL)を大きく改善することができます。
PMS・PMDD(月経前のこころと身体の不調)
PMS(Premenstrual Syndrome)とは
PMSとは「月経前症候群」のことを指し、排卵後から月経(生理)が始まる数日前までの期間に、こころと身体にさまざまな不調が現れる状態です。 月経が始まると自然に症状が軽くなるのが特徴で、働く女性や学生、育児中の方など、幅広い世代に見られます。
PMSの主な症状
- 精神的症状:イライラ、怒りっぽさ、気分の落ち込み、不安感、情緒不安定
- 身体的症状:胸の張り、頭痛、むくみ、眠気、過食、便秘、疲労感
- 行動的変化:集中力の低下、仕事・家事のパフォーマンス低下、人間関係のトラブル
症状の出かたや強さには個人差があり、日常生活に支障をきたすほど重い場合もあります。
PMDD(Premenstrual Dysphoric Disorder)とは
PMDD(月経前不快気分障害)は、PMSの中でも精神的な症状が非常に重くなるタイプです。 以下のような症状が月経前に現れ、日常生活に大きな影響を与える場合、PMDDの可能性があります。
PMDDに特徴的な症状
- 抑うつ気分、絶望感、強い不安や焦燥感
- 感情の爆発(怒り、泣き出すなど)、衝動的な言動
- 自己否定、対人関係のトラブル
- 出勤・登校困難、社会生活の著しい制限
PMSと異なり、医療的な治療介入が必要なケースも多く、うつ病などの気分障害と誤診されることもあるため、注意が必要です。
PMS・PMDDの原因と背景
PMS・PMDDの明確な原因は完全には解明されていませんが、主に以下が関係しているとされています。
- 排卵後(黄体期)のホルモン変動(エストロゲンとプロゲステロンの急激な変化)
- 脳内の神経伝達物質「セロトニン」の機能低下
- 睡眠障害や自律神経の乱れ、ストレス感受性の強さも関与すると考えられています
PMS・PMDDに関するよくあるご質問(FAQ)
PMSとPMDDの違いはなんですか?
PMS(月経前症候群)は、月経前に心身の不調があらわれる状態ですが、PMDD(月経前不快気分障害)はその中でも精神的症状が特に重く、日常生活に支障をきたすレベルの状態です。PMDDは医療的な治療介入が必要なことも多く、うつ病との見分けが必要です。
PMSの症状はどのくらい前から出始めますか?
一般的には、排卵後から月経開始の3〜10日前にかけて症状が出始め、月経が始まると自然に軽快するのが特徴です。
PMSの症状は誰にでもありますか?
多くの女性が何らかのPMS症状を経験しますが、重症度や症状の種類は個人差が大きく、全く感じない方もいれば、日常生活が困難になるほどの方もいます。
PMSやPMDDは何歳くらいから起こりますか?
初潮後しばらくして排卵が安定してくる10代後半〜20代以降に多く見られ、閉経に向かうまでの期間にわたって症状が続くこともあります。
イライラや気分の落ち込みがあるのですが、PMSかうつ病かわかりません。
PMSやPMDDは周期的(月経に連動)に気分の変化が出るのが特徴です。うつ病は周期と関係なく続く傾向があります。正確な判断のためには、医師の診察や月経記録(アプリや日記)を活用して相談しましょう。
食欲が止まらず過食してしまいます。これもPMSですか?
はい、PMSの症状の一つに食欲増進・甘いものへの渇望・過食傾向が含まれます。血糖やホルモンの変化が影響しているとされており、生活改善や治療で緩和できる場合もあります。
PMSやPMDDは市販薬で治せますか?
軽度であれば市販の鎮痛薬やサプリで対応できることもありますが、重度のPMSやPMDDには医師による治療が必要です。自己判断での放置は避けましょう。
ピルはPMSやPMDDに効果がありますか?
はい、低用量ピルはホルモン変動を安定させることで、PMSやPMDDの症状を軽減する効果があります。体質や持病によっては使用できない場合もあるため、医師の判断が必要です。
PMSやPMDDは治りますか?一生続くのでしょうか?
PMSやPMDDは適切な治療とセルフケアによって大きく改善できる症状です。閉経に近づくと自然におさまることも多いですが、年齢に関係なく、つらさを感じた時点での治療が重要です。
PMSやPMDDの診断にはどんな検査をしますか?
特別な検査は不要なことも多く、症状と月経周期との関係を記録(PMS日記)することが診断の手がかりになります。必要に応じて、ホルモンや甲状腺機能などの血液検査を行うこともあります。
「月経(生理)前になると毎回つらい」「感情のコントロールができず人間関係に支障が出る」など、月経前の不調が生活の質(QOL)を下げている場合は、PMS・PMDDの可能性があります。
決して“気のせい”や“甘え”ではなく、れっきとした医療的ケアが必要な状態です。 ひとりで悩まず、婦人科にお気軽にご相談ください。あなたのつらさを、改善する方法があります。
月経に関連したトラブルの治療法について
月経異常、強い生理痛(=月経困難症)、PMS/PMDDなど、月経にまつわる不調は、治療によって改善が期待できます。 ここでは、婦人科で行われる主な治療法を3つのアプローチに分けてご紹介します。
1. ホルモン療法(内服・注射によるホルモンの調整)
ホルモン療法は、月経周期を整えたり排卵を抑えたりすることで、月経に関連するさまざまな症状を改善する治療法です。症状の種類や年齢、妊娠の希望の有無などに応じて適切な方法が選ばれます。
低用量ピル(LEP製剤)
- 月経周期を整えるとともに、出血量の軽減、月経(生理)痛の緩和にも効果があります。
- PMS(月経前症候群)の症状緩和にも有効です。
- 避妊効果もあるため、避妊を希望する方にも適しています。
黄体ホルモン療法(プロゲスチン製剤)
- 排卵を抑える作用により、月経量を減らしたり、月経をコントロールする目的で使用されます。
- 無月経やPCOS(多嚢胞性卵巣症候群)に対する治療にも適応されます。
GnRHアゴニスト
- 一時的に女性ホルモンの分泌を抑えることで、子宮筋腫や子宮内膜症の症状を軽減します。
- 閉経後に似た状態を人工的に作るため、使用期間や副作用への注意が必要です。
ホルモン補充療法(HRT)
- 更年期障害や早発卵巣不全(POI)に伴うホルモン低下による症状(ホットフラッシュ、不眠、気分の落ち込みなど)を改善します。
注意:ホルモン療法や低用量ピルには、血栓症などの副作用や禁忌(喫煙・持病のある方など)があるため、必ず医師の診察と指導のもとで使用することが重要です。
2. 手術療法(器質的な原因がある場合)
月経異常や強い月経(生理)痛の原因が、子宮筋腫やポリープなどの明確な病気(器質的疾患)である場合には、手術療法が選択されることもあります。
子宮鏡手術(内視鏡)
- 子宮内膜ポリープや粘膜下筋腫の切除を、身体への負担が少ない日帰り手術で行うことができます。
子宮動脈塞栓術(UAE)
- 子宮筋腫に栄養を送る血管を塞ぎ、筋腫を縮小させる治療法です。過多月経の改善に有効です。
- 当院では実施していないため、必要に応じて連携医療機関をご紹介いたします。
子宮摘出術
- 筋腫や子宮腺筋症の症状が非常に重く、薬物治療が無効な場合に検討されます。
- 妊娠を希望されない方が対象となり、当院では連携病院にて対応いたします。
3. 生活指導・セルフケア
生活習慣の見直しも、月経トラブルの改善には重要です。ホルモン分泌や自律神経のバランスを整えるため、以下のような生活指導が行われます。
- ストレスのコントロール(睡眠・休息・趣味・カウンセリングなど)
- 適正な体重の維持(過度なダイエットや肥満は月経異常の原因に)
- 禁煙・アルコール制限(ホルモンや血流への影響を減らす)
- 栄養バランスの整った食事(鉄分不足やビタミンD欠乏は月経トラブルを悪化させることがあります)
補足|その他の治療法
症状やご希望に応じて、以下のような補助的治療も選択されます。
- 鎮痛薬(NSAIDs):月経(生理)痛や炎症に対して広く使用される基本的な治療薬です。
- 漢方薬:体質や月経のタイプに合わせて処方され、副作用が比較的少なく、長期使用にも適しています。(例:当帰芍薬散、加味逍遙散、桂枝茯苓丸など)
「月経(生理)がつらいのは仕方ない」と我慢している方も多いかもしれません。 しかし現在は、症状やライフスタイルに応じて選べる治療法が増えており、適切な医療介入によって生活の質(QOL)を大きく改善することが可能です。
気になる症状がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。患者さま一人ひとりに合わせた治療法をご提案いたします。