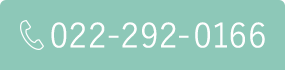妊娠できない・くり返す流産
 「赤ちゃんが欲しいのに、なかなか授からない…」
「赤ちゃんが欲しいのに、なかなか授からない…」
「妊娠したけれど、また流産してしまった…」
そんな不安や悲しみを感じている方へ。
妊娠や出産は、決して当たり前のことではなく、いくつもの小さな奇跡が積み重なってはじめて成立するものです。
月に1度の排卵、精子と卵子の出会い、受精、子宮内膜への着床、胎盤の形成、赤ちゃんの成長…どれもがスムーズに進まなければ、命は誕生しません。
日本では、夫婦の約5組に1組が不妊の悩みを抱えているとされ、さらに流産や不育症といった妊娠後のトラブルも決して珍しくありません。
「どうして私だけが…」と責める必要はありません。あなたと同じように悩んでいる方は、実はたくさんいらっしゃいます。
特に近年は、女性の社会進出やライフスタイルの多様化、晩婚化の影響で、妊娠のタイミングや体の変化に気づく機会が遅れる傾向にあります。気づかないうちに「妊娠しづらい年齢」に差しかかっていることもあるのです。
「不安だけど、どこに相談すればいいのかわからない…」
「まだ不妊って決まったわけじゃないから受診しづらい…」
そんな方こそ、まずは一度、気軽にご相談ください。
あなたの悩みに寄り添いながら、今できることを一緒に考えていきます。
不妊症とは?
 「不妊症」という言葉を聞くと、「私はもう妊娠できないの?」と不安になる方もいるかもしれません。
「不妊症」という言葉を聞くと、「私はもう妊娠できないの?」と不安になる方もいるかもしれません。
医学的には、避妊をせずに1年間、夫婦生活をしていても妊娠しない場合に「不妊症」と診断されます。 また、女性が35歳を超えている場合には、半年を目安に検査や相談を始めることがすすめられています。
妊娠は、以下のような複数のステップが問題なく進んで初めて成立します
- 卵巣から卵子が排卵される
- 卵管で精子と卵子が出会い、受精する
- 受精卵が子宮へ移動し、内膜に着床する
- 胎盤ができ、赤ちゃんが育っていく
このどこか1つでもうまくいかないと、妊娠には至りません。 そのため、不妊症の原因は人によってさまざまで、複数の要因が重なっていることもよくあります。
特に女性の場合、年齢が妊娠力(妊孕性)に大きく影響します。 卵子は年齢とともに「数」も「質」も低下していくため、30代後半からは自然妊娠の確率が下がり、流産のリスクも高まります。 一方で、男性にも加齢による精子の運動率低下やDNAの傷つきやすさといった影響が見られるため、ご夫婦(カップル)で一緒に考えることが大切です。
「不妊かもしれない」と感じたとき、または「もしかして年齢的にそろそろ検査だけでもしておこうかな」と思ったときが、相談のタイミングです。
当院では、無理なく受けられる検査からスタートし、必要に応じて次のステップを丁寧にご説明しています。 「まずは知ること」「体を知ること」から始めてみましょう。
不妊の原因はどこにある?
 不妊の原因は、「女性側」「男性側」「両方にある場合」「原因がはっきりしない場合」の4つに分けられます。 実際には、ひとつの原因だけでなく、いくつかの要素が重なっていることも多くあります。
不妊の原因は、「女性側」「男性側」「両方にある場合」「原因がはっきりしない場合」の4つに分けられます。 実際には、ひとつの原因だけでなく、いくつかの要素が重なっていることも多くあります。
女性側の原因
妊娠に必要な「排卵」「受精」「着床」のいずれかにトラブルがあると、妊娠しづらくなります。 代表的なものをご紹介します。
1. 排卵がうまくいかない(排卵障害)
排卵とは、卵巣の中で育った卵子が飛び出すことです。これが毎月1回きちんと起きていないと、妊娠はできません。
主な原因としては以下のものがあります
- 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS):排卵しづらい体質。比較的よく見られる排卵障害のひとつです。
- 高プロラクチン血症:乳汁を出すホルモン「プロラクチン」が高すぎて排卵が止まってしまう状態。
- ストレスや急激な体重変化:過度なダイエットや激しい運動、精神的なストレスが排卵を止めることもあります。
- 早発卵巣不全(POI):40歳未満で卵巣機能が低下すること。卵子が早く減ってしまいます。
2. 卵管が詰まっている(卵管因子)
卵子と精子が出会う場所は卵管です。卵管が詰まっていたり、癒着していたりすると、受精できません。
原因の多くは以下のようなものです
- クラミジア感染:過去の性感染症が原因で、知らないうちに卵管が傷ついていることがあります。
- 子宮外妊娠の既往:卵管に炎症やダメージが残っていることがあります。
- 腹部手術歴:虫垂炎(盲腸)や帝王切開の後などに、癒着が起こることがあります。
3. 子宮に問題がある(子宮因子)
受精卵が着床するためには、子宮内膜がふかふかのベッドのように整っていることが必要です。子宮に異常があると着床できない・流産しやすいことがあります。
- 子宮筋腫:特に子宮の内側(粘膜下)にできる筋腫は着床を妨げる可能性があります。
- 子宮内膜症:卵巣や子宮のまわりに炎症が起き、卵巣機能や卵管の動きを低下させます。
- 子宮内膜ポリープ:子宮の内側にできた良性のポリープが、着床を邪魔することがあります。
- 子宮内癒着症(アッシャーマン症候群):手術後などに子宮の内側が癒着してしまう状態です。
4. 年齢による卵子の老化
女性の卵子は、生まれたときから卵巣にあるもので一生を過ごします。そのため、加齢とともに卵子の質も数も低下していきます。
- 35歳をすぎると妊娠率は低下し、40代では急激に下がることが知られています。
- AMH検査(抗ミュラー管ホルモン)を行うことで、卵子の残り具合(卵巣予備能)を調べることができます。
男性側の原因
男性にも妊娠の鍵があります。精子の数・動き・形・通り道などが問題になることがあります。
1. 精子の数が少ない・動きが悪い(造精機能障害)
- 精子の数が少ない(乏精子症)
- 精子があまり動かない(精子無力症)
- 精子の形が異常(奇形精子症)
精子の状態は、病気・ストレス・生活習慣(喫煙・飲酒・肥満)などの影響を受けます。
2. 精子の通り道がふさがっている(精路通過障害)
- 精管閉塞:精子を運ぶ管がふさがれていると、精子が外に出てきません(無精子症)。
- 先天的に精管がない人もいます(両側精管欠損症)
3. 射精がうまくいかない(性機能障害)
- 勃起不全(ED):精神的なストレスや生活習慣病(糖尿病など)で起こります。
- 射精障害:神経の異常、糖尿病、過去の手術などが関係していることもあります。
両方に原因がある場合
不妊のカップルの約30%ほどは、「女性にも男性にも、それぞれ原因がある」といわれています。 たとえば、女性の排卵が不安定で、男性の精子も少し弱っている…といったように、少しずつの原因が重なると妊娠しにくくなるのです。
原因が見つからない場合(原因不明不妊)
すべての検査をしても、明確な異常が見つからないことがあります。これを「原因不明不妊」と呼びます。 このような場合も、タイミングや人工授精、体外受精などを試すことで妊娠に至るケースはあります。
原因不明とはいっても、妊娠できないという意味ではありません。現代の医療でまだ見つけきれていない微細な問題(免疫の反応や着床のしくみなど)が関係していることもあると考えられています。
不妊症の検査内容
不妊の原因は、人によってさまざまです。まずは「体のどこに妊娠しづらい原因があるのか」を調べることから始めます。
検査といっても、痛みが強いものは少なく、多くが短時間で終わります。外来でできる検査がほとんどなので、安心してください。
女性の検査では、以下のようなことを調べます。
- ホルモンの状態
血液検査で、排卵に関係するホルモンのバランスを調べます。
卵子の残り具合(卵巣の力)を調べるAMHという項目もあります。 - 子宮や卵巣の状態
内診のときに行う「超音波検査」で、卵子の育ち具合や子宮の内膜の厚さ、筋腫やポリープの有無を見ます。 - 卵管が詰まっていないか
「卵管通水検査」や「卵管造影検査」で、卵子と精子の通り道がきちんと開いているかを確認します。(2025年9月現在は当院では卵管通水検査をすることができます。) - 子宮の中の様子
「子宮鏡検査」で、子宮の中にポリープや癒着がないかを小さなカメラで直接見ます。 - 基礎体温表の記録
毎朝体温を測ってグラフをつけることで、排卵のリズムを確認できます。
男性の検査では、精子の状態を調べます。
- 精子の数
- 動きのよさ(運動率)
- 形のよさ(正常な割合)
さらに詳細な検査が必要と判断した場合は、泌尿生殖の専門施設にご紹介します。
不妊の原因は、女性だけにあるとは限りません。 実は、半分近くのカップルで、男性側にも原因があると言われています。 そのため、ご夫婦で一緒に検査を受けることをおすすめしています。
不妊治療の方法
検査の結果に応じて、治療を始めていきます。治療は、体への負担が少ない方法から段階的に進めます。無理のないペースで進めていけるので、安心してください。
1. タイミング療法(自然な妊娠をめざす方法)
排卵日を予測し、妊娠しやすいタイミングにあわせて夫婦生活を持つ方法です。 排卵を助ける飲み薬や注射を使うこともあります。
2. 人工授精(AIH)
採取した精子を元気なものだけ選んで、排卵にあわせて子宮に注入する方法です。 処置はすぐに終わり、痛みもほとんどありません。 性交がうまくいかない方や、精子の運動率がやや低い方に向いています。
3. 体外受精(IVF)
体の外で卵子と精子を受精させて、受精卵を子宮に戻す方法です。 精子が少ない場合や、これまでの治療で妊娠に至らなかった方に行います。
※連携クリニックをご紹介させていただきます。 不妊症の方は、不妊治療終了後も月経異常や早発卵巣不全など、ご自身のヘルスケアが必要なことが多いです。紹介後、不妊治療終結後も当院でしっかりヘルスケアをしていきます。ぜひご相談下さい。
このように、不妊治療は「いきなり難しいことをする」わけではありません。 あなたの体の状態やライフスタイルに合わせて、そのときにできるベストな方法を一緒に考えていきます。
不育症とは?
「妊娠はできるのに、赤ちゃんが育たない…」
不育症とは、妊娠はするけれど、流産や死産をくり返してしまい、生児(赤ちゃん)を抱くまでに至らない状態のことをいいます。 厚生労働省や専門学会では、2回以上の流産・死産・早期新生児死亡を経験した方に対して、不育症の検査や治療をすすめています。
流産はめずらしいことではありません。
実は、妊娠全体の約15〜20%は流産で終わるとされています。
特に、妊娠12週未満の「初期流産」の多くは、偶然起こる胎児の染色体異常が原因であることが多く、特別な病気ではありません。
しかし、2回以上の流産が続く場合は、体質や病気など、からだの中に何か原因がある可能性が高くなります。 そのため、「たまたまではないかもしれない」と感じたときには、一度検査を受けてみることをおすすめします。
不育症の主な原因と検査
不育症の原因はひとつではなく、さまざまな要素が関わっています。 中には、ご本人が気づかないまま長く過ごしているケースもあります。
主な原因には次のようなものがあります
ご夫婦いずれかの染色体異常
見た目は健康でも、染色体の並び方に「転座(バランスは取れているが配置が違う)」という変化があると、赤ちゃんに遺伝したときに流産の原因になることがあります。
子宮の形の異常
中隔子宮(子宮の中に膜のような仕切りがある状態)や、粘膜下筋腫、ポリープなど、子宮内で赤ちゃんがうまく育ちにくい形をしていることがあります。
免疫の異常
抗リン脂質抗体症候群(APS)という免疫の病気では、体の中で血が固まりやすくなり、胎盤への血流が悪くなって流産につながることがあります。
血液の凝固異常(血が固まりやすい体質)
プロテインSやプロテインCの欠乏などがあると、妊娠中の血流が滞りやすく、胎児の発育に悪影響を与えることがあります。
ホルモンバランスの乱れ
甲状腺の働きが弱い(甲状腺機能低下症)、糖尿病、高プロラクチン血症など、妊娠を維持するホルモンがうまく働かないと流産のリスクが高まります。
生活習慣の影響
喫煙、カフェインのとりすぎ、肥満、過度なダイエット、強いストレス、睡眠不足なども、妊娠の維持に影響を与えるとされています。
検査はどうやって行うの?
検査は、血液検査、超音波検査、子宮鏡検査、染色体検査などを組み合わせて行います。
たとえば、染色体の検査は夫婦それぞれの血液から調べますし、子宮の形は超音波や子宮鏡、必要に応じてMRIで確認します。
免疫や血液の性質(血栓ができやすい体質)なども血液検査でわかります。 これらをすべて一度に行うのではなく、必要に応じて順番に進めるので、ご安心ください。
不育症の治療方法
検査で原因がわかった場合には、それに合わせた治療を行います。 治療といっても、すべてが大がかりなものではありません。飲み薬や注射、生活習慣の見直しなど、できることから丁寧に取り組んでいきます。
体質・病気に応じた治療
血が固まりやすい体質の場合
抗リン脂質抗体症候群などがある方には、「アスピリン」や「ヘパリン」という血をサラサラにする薬を妊娠初期から使用します。これにより、胎盤への血流が改善し、妊娠を継続しやすくなります。
ホルモンの異常がある場合
甲状腺ホルモンや黄体ホルモンを補う治療を行い、妊娠をサポートします。血糖値やインスリン抵抗性の異常がある方には、生活改善や内服治療を組み合わせることもあります。
子宮の形に異常がある場合
中隔子宮や筋腫など、子宮の構造に問題があるときは、子宮鏡を使った手術で形を整えることもあります。
染色体の異常がある場合
ご夫婦どちらかに転座などの染色体異常がある場合は、「遺伝カウンセリング」を受けて、今後の妊娠の方針を一緒に考えていきます。
原因が見つからない場合も、治療できます
不育症の中には、明確な原因が見つからない「原因不明不育」もあります。 このような場合でも、黄体ホルモンの補充や、低用量アスピリンの内服、漢方療法、心理的サポートなどを行うことで、妊娠を維持できる可能性があります。
「原因がわからないから、何もできない」わけではありません。一緒に、あなたに合った方法を探していきましょう。
不妊症・不育症に関する「よくあるご質問(FAQ)」
不妊症と不育症の違いは何ですか?
不妊症は「妊娠できない状態」のことを指します。避妊をしていないにもかかわらず、1年以上妊娠に至らない場合に不妊症と診断されます。 一方、不育症は「妊娠はするけれど、流産や死産を2回以上くり返す場合」を指します。 どちらも、早めの相談と適切な検査が大切です。
何歳くらいから妊娠しにくくなりますか?
一般的に35歳を過ぎると、卵子の質や妊娠率が下がり、40代ではさらにその傾向が強くなります。早めの検査が安心につながります。
月経(生理)が来ていれば排卵もしているのですか?
月経(生理)があっても、必ずしも排卵しているとは限りません。基礎体温やホルモン検査などで確認することができます。
検査や治療は痛いですか?
多くの検査は短時間で終わり、痛みも少ないものがほとんどです。不安なことがあれば事前にご相談ください。
夫が検査や治療に協力してくれません…。
不妊の原因は男女半々といわれており、ご夫婦で一緒に取り組むことが大切です。男性にもできるだけわかりやすく説明しますので、まずは一緒に来院していただけると安心です。
仕事をしながらでも通えますか?
はい。検査や治療は多くが短時間で終わるものです。スケジュール調整やご希望に応じた通院ペースもご相談いただけます。
一度流産しただけでも不育症の検査を受けた方がよいですか?
初めての流産は、胎児側の染色体異常など偶然によることが多く、すぐに不育症と診断されるわけではありません。
ただし、流産や死産を2回以上くり返す場合には、不育症の検査を受けることが推奨されています。 不安なことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。
不妊治療はすべて自由診療ですか?
2022年から保険適用範囲が拡大され、タイミング法・人工授精・体外受精なども条件によって保険が使えるようになりました。年齢や回数の制限があるため、詳しくはご相談ください。
精子や卵子の検査結果が悪かったら、もう妊娠できませんか?
一度の結果だけで判断せず、必要に応じて再検査や別の方法を提案します。卵子や精子の状態に合った治療で妊娠される方もたくさんいらっしゃいます。
治療にどのくらい時間がかかりますか?
個人差はありますが、まずは3〜6か月を目安に治療を進める方が多いです。焦らず、一歩ずつできることを積み重ねていきましょう。